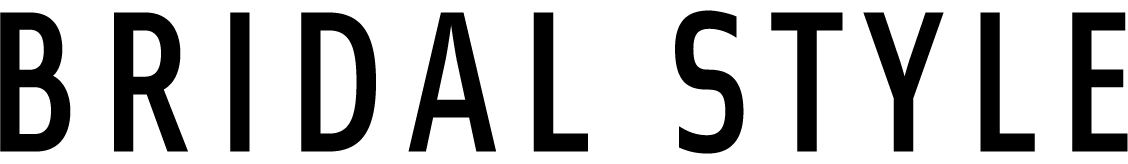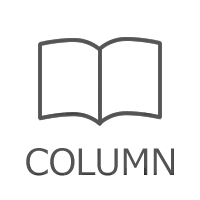【結婚式の引出物】その由来と贈り分けや選び方のポイントをご紹介!

前回の記事「【結婚式の映像】結婚式の映像にはどんな種類がある?種類ごとの特徴や依頼先をご紹介!」では、結婚式の種類について詳しく解説しました。
この記事では、結婚式準備のポイント「披露宴アイテムの決定」の中の「引出物・プチギフト」から「引出物」に焦点を当ててみていきましょう。
結婚式で必ず用意しなければならない引出物。結婚式に出席した経験がある人はもらったことがありますよね。引出物選びはセンスが問われるため、どうやって選べばいいのか悩んでしまう人もいるはず。
そこで今回は引出物の由来やそれぞれの意味、特徴をご紹介します。贈り分けや引出物を選ぶときのポイントなどもご紹介しているので、引出物選びの参考にしてみてください。
婚式の引出物とは?その目的と意味

結婚式で交換されるご祝儀とお返しの品。この「お返しの品」として定着している引出物には、ゲストへの感謝の気持ちを伝える大切な役割があります。単なるお返しではなく、結婚式に参列してくださったゲストとの思い出の品として、そして新郎新婦からの心のこもった贈り物として、長く記憶に残るものとなるでしょう。昨今では、ご祝儀の金額に見合った品物を選ぶことも大切なマナーとされています。また、引出物を通じてお二人らしさや結婚式のテーマを表現するカップルも増えてきました。
ゲストへの感謝を形にする贈り物
結婚式当日、遠方からわざわざ時間を作って来てくださったゲストの方々。そんな大切なゲストへの感謝の気持ちを形にするのが引出物です。お二人の新しい門出を祝福してくださった方々への気持ちを込めて、心を込めて選びたいものですね。ゲストの年齢層や生活スタイル、お二人との関係性など、さまざまな要素を考慮しながら、一つ一つ丁寧に選んでいきましょう。引出物選びは結婚式準備の中でも特に重要な要素の一つとされており、近年では早い段階から準備を始めるカップルが増えています。また、引出物を通じて新郎新婦の気持ちやセンスを表現できる貴重な機会でもあるのです。
お祝いのお返しとしての役割
結婚式では多くのゲストからご祝儀をいただきます。その気持ちへのお返しとして、引出物を贈ることは現代では一般的な習わしとなっています。単なるお返しではなく、お二人の門出を祝福してくださった方々への感謝の意を込めた贈り物として、引出物は大切な役割を担っているのです。近年では、ご祝儀の金額に応じて引出物の内容を変える「贈り分け」という考え方も一般的になってきました。また、引出物は結婚式後もゲストの暮らしの中で使われ続けることで、お二人との思い出を紡ぐアイテムとしても大切な意味を持っています。
結婚式の引出物の由来
平安時代から続く日本の伝統的な贈り物である引出物。その長い歴史の中で形を変えながらも、「感謝の気持ちを伝える」という本質は変わることなく、現代まで受け継がれています。引出物の歴史を知ることで、その意味や重要性をより深く理解することができるでしょう。日本の結婚式の伝統や文化の中でも、特に重要な位置を占める引出物の歴史は、私たちの大切な文化遺産の一つとも言えます。
平安時代から続く伝統
引出物の起源は平安時代にまで遡ります。当時の宴会では、主催者が招待客へのお礼として馬を贈ることがありました。その馬を「庭に引き出して披露した」ことから、招待客への土産物を「引出物」と呼ぶようになったとされています。時代を経て贈り物の内容は変化しましたが、「感謝の気持ちを込めた贈り物」という本質は今も変わっていません。この伝統は、日本の結婚式文化の中でも特に長く受け継がれてきた習わしの一つであり、現代の結婚式でも欠かすことのできない重要な要素となっています。また、この伝統には日本特有のおもてなしの心が色濃く表れているとも言えるでしょう。
時代とともに変化する贈り物の形
時代とともに引出物の形は大きく変化してきました。かつては婚礼料理の一部をお土産として持ち帰ることが一般的でしたが、衛生面への配慮から現在のような品物の贈呈へと変わっていきました。近年では、カタログギフトや体験型ギフトなど、選択肢も多様化しています。ゲストの好みや生活スタイルに合わせて選べる現代の引出物は、より一層感謝の気持ちを伝えやすいものとなっているのです。また、デジタル化が進む現代では、オンラインカタログや電子感謝状など、新しい形の引出物も登場してきています。このように、引出物は時代のニーズに合わせて柔軟に形を変えながら、その本質的な意味を守り続けているのです。
引出物は何品用意するべき?

引出物を決めようと思っても、何品用意するべきか悩んでしまう人も多いでしょう。引出物は一般的に「引出物(記念品)」「引菓子」「しきたり品(縁起物)」の3品用意します。これはご祝儀と同様に割り切れる数は縁起が悪いとされているため、3・5・7などの奇数個用意するのが良いとされているからです。
しかし、引出物は地域によってしきたりが違ってくるので注意が必要。住んでいる地域の風習だけではなくそれぞれの地元の風習も考慮する必要があるので、親御さんに相談してから決めるようにしましょう。
基本の3点セットについて
3点セットの基本構成は、メインとなる「引出物」、お菓子などの「引菓子」、そして縁起物としての「しきたり品」です。この組み合わせには、それぞれに意味があり、ゲストへの感謝の気持ちを様々な形で表現することができます。また、3点セットは持ち帰りやすい量として、ゲストへの負担も考慮された理想的な数とされています。予算や準備の手間を考えても、3点セットは多くのカップルにとって現実的な選択となっているのです。
地域による違いと確認のポイント
引出物の数や内容は、地域によって大きく異なることがあります。例えば、関東と関西では引出物に対する考え方や習慣が異なることもあります。また、地方によっては特定の引出物が定番となっているケースもあるでしょう。以下のポイントを事前に確認しておくことをおすすめします。
- 両家の出身地での一般的な引出物の数
- 地域特有のしきたり品の有無
- 親族から期待される引出物の種類
- 地元での一般的な相場
このような地域性への配慮は、両家の親族やゲストへの心遣いとなり、結婚式をより円滑に進めることができます。特に、遠方から来られるゲストがいる場合は、その地域の習慣も考慮に入れると良いでしょう。
「引出物」「引菓子」「しきたり品」の意味と特徴をご紹介!

先ほどご紹介したように引出物は「引出物」「引菓子」「しきたり品」の3品を用意するのが基本です。ここでは、それぞれの意味と特徴を詳しくみていきましょう。
引出物
記念品としての役割
メインの引出物は、お二人の結婚式を記念する特別な贈り物です。以前は同じ品物をゲスト全員に贈るのが一般的でしたが、最近では一人一人に合わせた品物を選ぶ「贈り分け」が主流になってきています。記念品としての価値だけでなく、実用性も重視されるようになってきており、ゲストの日常生活の中で末永く使っていただけるものを選ぶことが大切です。
選び方のポイント
引出物選びで重要なのは、ゲストの立場に立って考えることです。以下のポイントを参考に、ゲストに喜んでいただける品物を選びましょう。
- 年齢層や性別に合わせた品物選び
- 持ち帰りやすさへの配慮
- 日常生活での使いやすさ
- 品質とブランド価値のバランス
- 贈り分けを行う場合の予算配分
引菓子
おすそ分けの意味
引菓子には、結婚式の喜びを参列できなかった方々とも分かち合いたいという気持ちが込められています。ゲストが自宅に持ち帰り、家族や友人と共に楽しむことができる品物として、結婚式の余韻を広げる役割も担っています。また、お菓子は「縁を結ぶ」という意味も持つことから、めでたい席にふさわしい贈り物とされています。
定番の種類と選び方
引菓子は、以下のような点に気を配って選びましょう。
- 日持ちの良さ
- 見た目の華やかさ
- 食べやすさと取り分けやすさ
- 季節感への配慮
- 包装や掛け紙のデザイン
しきたり品
縁起物の意味
しきたり品は、新郎新婦の幸せな未来への願いを込めた縁起物です。長寿や子孫繁栄、夫婦円満など、様々な願いが込められた伝統的な品々が選ばれます。地域によって異なる場合もありますが、一般的には以下のようなものが選ばれます。
- かつお節(夫婦円満の象徴)
- 梅干し(長寿の願い)
- 昆布(子孫繁栄)
- 飴菓子(末永い甘い生活)
地域性への配慮
しきたり品は特に地域性が強く表れる品物です。両家の出身地や、結婚式を挙げる地域の習慣を確認しながら選びましょう。場合によっては、地域ごとに異なるしきたり品を用意することも検討してください。また、現代風にアレンジされたしきたり品も増えてきているので、お二人らしさを表現する機会としても活用できます。
引出物の種類と特徴
近年、引出物の選択肢は大きく広がっています。従来の実物の贈り物に加え、カタログギフトという新しい形式も一般的になってきました。それぞれに特徴があり、ゲストの年齢層や結婚式のスタイルによって、最適な選択は変わってきます。ここでは、主要な引出物の種類とそれぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
カタログギフト
メリット
カタログギフトは、ゲストが自分の好みで商品を選べる現代的な引出物です。食器やタオルなどの定番商品から、体験型ギフトまで幅広い商品の中から選ぶことができ、ゲストの満足度も高いのが特徴です。また、持ち帰りの負担が少なく、遠方からのゲストにも配慮した選択となります。特に若い世代のゲストには、自分で選べる楽しみがあると好評です。
デメリット
カタログの有効期限があることや、お気に入りの商品が品切れになる可能性があるなどの制約があります。また、目上の方には実物の贈り物の方が適している場合もあり、世代によって受け取り方に差が出る可能性があります。商品を選ぶ手間がゲストにかかることも、デメリットの一つと言えるでしょう。
選ぶ際の注意点
カタログギフトを選ぶ際は、以下の点に注意を払いましょう。
- 掲載商品の品質とブランド価値
- カタログの有効期限
- 商品の価格帯のバランス
- 交換方法の分かりやすさ
- 配送料の有無と条件
実物の引出物
メリット
実物の引出物は、お二人の想いを直接形にして贈ることができます。特に伝統的な品物や高級ブランドの商品は、格式のある贈り物として喜ばれます。また、その場で商品を手に取ることができ、お二人からの感謝の気持ちがより直接的に伝わるという利点があります。
デメリット
ゲスト全員の好みに合わせることが難しく、また持ち帰りの負担が大きくなる可能性があります。特に食器類は割れ物であることから、持ち帰りに気を使う必要があります。また、在庫管理や配送の手配など、準備の手間も考慮が必要です。
選定時の確認事項
実物の引出物を選ぶ際は、以下の点を必ず確認しましょう。
- 商品の品質と耐久性
- 包装や梱包の安全性
- 持ち運びのしやすさ
- 納品時期と在庫状況
- アフターサービスの有無
最近では「贈り分け」する人が多い!ゲスト別の金額相場は?

ひと昔前までは引出物の相場は「飲食代の3分の1」が目安とされ、ゲスト全員に同じものを贈っていました。しかし、現在では「おもてなし」に重点を置くようになりゲストの顔ぶれに合わせて品物を変える「贈り分け」が主流になりつつあります。贈り分けとは、ゲストとの関係性や年齢層に応じて引出物を変えることです。近年では、よりきめ細やかなおもてなしとして定着してきています。ただし、贈り分けを行う際は、差が目立たないよう配慮することが大切です。
なぜ贈り分けが必要なのか
贈り分けは、ゲストへのきめ細やかな配慮を形にする方法として注目されています。ご祝儀の金額への配慮はもちろんですが、それ以上に各ゲストの生活スタイルや好みに合わせた贈り物をすることで、より一層の感謝の気持ちを伝えることができます。また、世代によって好まれる品物が大きく異なることも、贈り分けが必要とされる理由の一つです。
贈り分けの具体的な方法
贈り分けを行う際は、大きく3つのグループに分けるのが一般的です。親族、上司、友人・同僚という分け方です。これ以上細かく分けてしまうと、管理が煩雑になってしまう可能性があります。それぞれのグループに対して、以下のような配慮を行います。
- 親族には伝統的で格式のある品物
- 上司には品格のある実用的な品物
- 友人・同僚には使いやすく、センスの良い品物
贈り分け時の注意点
贈り分けを行う際は、以下のような点に気を配る必要があります。
- 外見上の差が目立たないように包装を工夫する
- 同じテーブルの方には同じ引出物を贈る
- 親族内での贈り分けは特に慎重に行う
- 引出物の内容が周りに分からないよう配慮する
- 記録をしっかりと残し、混乱を避ける
ゲスト別の金額相場
引出物の金額相場は、一般的にご祝儀の1割程度と言われています。しかし、これはあくまでも目安であり、ゲストとの関係性や地域性によって適切な金額は変わってきます。ここでは、ゲスト別の具体的な相場と選び方のポイントをご紹介します。
引出物選びは結婚式準備の中でも重要な要素の一つです。ゲストへの感謝の気持ちを形にする大切な機会であり、慎重に選ぶ必要があります。以下、ゲスト別の金額相場や成功する引出物選びのポイント、よくある疑問についてさらに詳しく解説していきます。
親族への贈り方
親族への引出物は、一般的にご祝儀の15〜20%程度が相場とされています。特に両親や祖父母には、より高価で格式のある品を選ぶことが多いです。伝統的な和食器セットや高級ブランドの小物、有名窯元の茶器セットなどが人気です。ただし、実用性も考慮し、日常生活で使える品物を選ぶことも大切です。例えば、高級な寝具セットや、ブランドのキッチン用品なども良い選択肢となるでしょう。親族への贈り物は特に重要視されるため、両家の意向も踏まえながら慎重に選びましょう。また、兄弟姉妹など、年齢が近い親族には、少し現代的なテイストの品物を選ぶのも良いアイデアです。
上司への配慮
上司への引出物は、ご祝儀の12〜15%程度が目安となります。品格があり、かつ実用的な品物が適しています。高級ペンセットやブランドの革小物、名入れグラス、高級ワインなどが定番です。ただし、あまりに高価すぎる品物は逆効果になる可能性もあるので注意が必要です。上司の趣味や嗜好がわかっている場合は、それに合わせた選択をするのも良いでしょう。例えば、ゴルフ好きの上司にはゴルフ用品、読書家の上司には高級な書籍セットなど、個性に合わせた選択ができれば理想的です。また、会社の慣習や業界の傾向なども考慮に入れ、適切な品を選びましょう。上司への贈り物は、今後の関係性にも影響する可能性があるため、十分な配慮が必要です。
友人・同僚への選び方
友人や同僚への引出物は、ご祝儀の10〜12%程度が一般的です。若い世代には、カタログギフトや体験型ギフトが人気です。実用的でありながらもデザイン性の高い生活雑貨なども喜ばれます。例えば、スタイリッシュなキッチン家電、おしゃれな照明器具、高品質なタオルセットなどが好まれます。友人ならではの関係性を活かし、少しユニークな品物を選ぶのも良いでしょう。例えば、二人の思い出の場所にちなんだ品物や、共通の趣味に関連したアイテムなど、個人的なつながりを感じられる贈り物は特に喜ばれます。また、同僚の場合は、職場での使用を考慮した品物(例:スタイリッシュなステーショナリーセットやオフィス用品)も良い選択肢となります。友人・同僚への贈り物は、カジュアルすぎず、かつ堅苦しくならない絶妙なバランスが求められます。
引出物選びの5つのポイント

引出物の種類はたくさんあるので、どれを選べばいいのか迷ってしまいますよね。ここでは、ゲストに喜ばれる引出物を選ぶために気を付けるべきポイントをご紹介します。
かさばらない物を選ぶ
ゲストの持ち帰りの負担を考え、コンパクトで軽量な品物を選びましょう。特に遠方からのゲストには配慮が必要です。折りたたみ式のアイテムや、小型でも高品質な商品などが適しています。例えば、折りたたみ傘、コンパクトな調理器具、薄型のタブレットケースなどが良いでしょう。また、最近では、体験型ギフトやデジタルギフトカードなど、物理的な大きさを持たない贈り物も人気です。これらは持ち帰りの負担がなく、特に若い世代に喜ばれます。ただし、あまりに小さすぎる品物は、軽視されているという印象を与える可能性があるので注意が必要です。適度な大きさと重量のバランスを考慮し、品物の価値と持ち運びやすさの両立を目指しましょう。
生活する中で使いやすいもの
日常生活で実際に使える品物を選ぶことが重要です。キッチン用品やバス用品、タオルなど、誰もが日常的に使用するアイテムは安全な選択肢となります。ただし、デザイン性も考慮し、特別感のある品を選びましょう。例えば、高級ブランドのタオルセット、デザイン性の高いキッチンツール、品質の良い寝具類などが適しています。最近では、スマートホーム製品(例:スマートスピーカー、IoT対応の家電)も人気があります。これらは日常生活を便利にするだけでなく、最新技術を取り入れた特別感も演出できます。また、季節を問わず使用できるアイテムを選ぶことで、年間を通じて使用してもらえる可能性が高まります。ゲストの生活スタイルを想像しながら、「あると便利」「使ってみたい」と思ってもらえるような品物を選びましょう。
自分では買わないもの
ゲストが普段自分では購入しないような、少し贅沢な品物を選ぶのも良いでしょう。高級ブランドの小物や、こだわりの食器セットなどが該当します。例えば、有名デザイナーとのコラボレーション商品、限定品のアクセサリー、高級食材のセットなどが考えられます。ただし、あまりに奇抜なものは避け、汎用性のある品物を選ぶことが大切です。最近では、サステナビリティに配慮した高級エコ製品(例:環境に優しい素材を使用したバッグや衣類)も注目されています。これらは、普段は手が出にくい価格帯でありながら、社会的意義のある贈り物として喜ばれる可能性があります。また、地元の伝統工芸品や、希少な素材を使用した商品なども、特別感のある贈り物として適しています。ゲストの興味や価値観を考慮しつつ、日常では手に入れにくい特別な品を選ぶことで、結婚式の思い出とともに大切にしてもらえる贈り物となるでしょう。
世代を考慮した選択
ゲストの年齢層によって、好まれる品物は大きく異なります。若い世代にはモダンでスタイリッシュな品物、年配の方には伝統的で落ち着いた品物が適しています。例えば、20代〜30代のゲストには、最新のテクノロジー製品(スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなど)やデザイン性の高い生活雑貨が人気です。40代〜50代には、高品質な日用品(高級タオル、ブランドの財布など)や、趣味に関連した品物(ワインセット、ゴルフ用品など)が喜ばれます。60代以上の方には、伝統的な和食器や、健康に配慮した商品(血圧計、マッサージ器など)が適しているでしょう。
ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、個人の趣味や生活スタイルによって好みは大きく異なります。可能であれば、事前にゲストの興味や嗜好を調べて、より最適な選択ができるようしましょう。また、世代を超えて喜ばれる「万能」な品物(高品質なタオルセットや、ブランドの小物など)を選ぶのも一つの方法です。世代に配慮しつつも、お二人らしさや結婚式のテーマを反映させた選択ができれば理想的です。
ゲストの立場に立った検討
最終的には、ゲストの立場に立って考えることが最も重要です。「もらって嬉しい」「使ってみたい」と思ってもらえる品物を選びましょう。ゲストの生活スタイルや趣味嗜好を考慮し、心のこもった選択をすることが、成功する引出物選びの鍵となります。例えば、子育て世代のゲストには家族で使えるアイテム(ピクニックセット、ファミリーゲームなど)、仕事中心の生活を送るゲストにはリラックスグッズ(アロマディフューザー、高級バスローブなど)を選ぶなど、ゲストの日常生活をイメージしながら選択することが大切です。
また、引出物を通じてお二人の個性や結婚式のテーマを表現することも考えられます。例えば、旅行好きなカップルであれば、世界各国の特産品セットや旅行用品を選ぶなど、お二人らしさを感じられる品物を選ぶのも良いでしょう。さらに、環境への配慮や社会貢献を重視する場合は、エシカルな商品や寄付付きの商品を選ぶことで、ゲストとともに社会的な価値を共有することもできます。
引出物のQ&A
ここでは、引出物についてよくある疑問についてお答えします!
Q1:いつから準備を始めるべき?
結婚式の引出物準備は、理想的には結婚式の6~8ヶ月前から始めることをおすすめします。この時期から準備を始めることで、以下のメリットがあります。
- 人気商品の早期確保
- ゆとりを持った選定プロセス
- 予算的な余裕
- カタログギフトの在庫確認
- デザインや内容の十分な検討時間
特に、カタログギフトや特注品を検討している場合は、早めの準備が重要となります。ただし、遅くとも結婚式の3ヶ月前までには方針を決定し、具体的な手配を始めることが望ましいでしょう。
Q2:引出物はいつ渡すのが一般的?
引出物の渡し方には、主に以下の3つの方法があります。
1. 披露宴会場での手渡し
- 最も伝統的な方法
- ゲストの席に事前に配置
- お開きの際に持ち帰り
2. 受付での手渡し
- 最近増えてきている方法
- ゲストの移動がスムーズ
- 荷物の管理がしやすい
3. 後日郵送
- 遠方のゲスト向け
- かさばる物や重い物の場合に適している
- 事前に郵送することを明確に伝える必要がある
Q3:郵送は失礼にあたる?
郵送自体は決して失礼ではありません。むしろ、以下のような状況では推奨される方法です。
- 遠方からのゲスト
- 高齢者や体の不自由なゲスト
- かさばる引出物の場合
- 欠席者への対応
注意点としては、以下の点に気をつける必要があります:
- 丁寧な説明文の同封
- 事前の明確な告知
- 丁寧な梱包
- 送付時期への配慮
Q4:両家の希望が異なる場合は?
両家の希望が異なる場合の対処法は以下の通りです。
1. 率直な対話
- お互いの希望と理由を聞く
- 妥協点を探る
2. 折衷案の検討
- 両家の意見を反映した引出物
- 予算や数量での調整
3. 専門家(プランナー)への相談
- 中立的な立場からのアドバイス
- 経験に基づく提案
4. 最終的には新郎新婦の意思決定
- 両家の意見を尊重しつつ、最終判断は二人で
Q5:引出物の相場を下回ってもいい?
引出物の相場については、以下のポイントを考慮しましょう。
- 相場はあくまで目安
- 金額よりも気持ちが重要
- ゲストとの関係性を考慮
- 実用性と特別感のバランス
- 予算に応じた柔軟な対応
具体的な目安
- 親族:ご祝儀の15~20%
- 上司:ご祝儀の12~15%
- 友人・同僚:ご祝儀の10~12%
Q6:カタログギフトと実物、どちらがおすすめ?
選択のポイント
カタログギフトのメリット
- ゲストが自由に選択可能
- 持ち運びが楽
- 多様な商品から選べる
実物ギフトのメリット
- その場で受け取れる
- 新郎新婦の想いが直接伝わる
- 特別感がある
Q7:持ち込み料について知っておくべきこと
持ち込み料の注意点
- 式場によって料金は異なる
- 通常、1点あたり1,000~5,000円程度
- 事前に式場に確認が必要
- 提携業者を利用すると無料の場合も
Q8:予算オーバーを防ぐコツは?
予算管理のためのアドバイス
- 早期の計画と見積もり
- ゲストリストの正確な把握
- セール時期の活用
- まとめ買いによる割引
- 柔軟な予算配分
- 代替案の検討
まとめ
引出物の意味や特徴などの基礎知識や引出物選びのポイントなどをご紹介しましたが、いかがでしたか。
引出物にはたくさんの種類があるので、カタログを見るとどれを選ぼうか悩んでしまうでしょう。
引出物は結婚式に来てくれたゲストへ感謝の気持ちを込めた贈り物です。ゲストの顔を思い浮かべながら、ゲストが喜んでくれるベストな引出物を選んでくださいね。