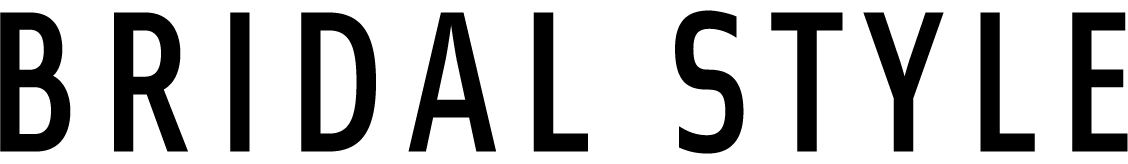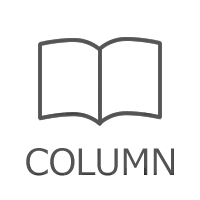【結婚式のゲスト人数】両家のゲスト数はどうする?人数差、人数が偏るときは?

前回の記事「【大人数の結婚式】メリット・デメリットは?気を付けたいポイントも!」では、大人数の結婚式のメリットやデメリットについてご紹介しました。
今回の記事では「両家のゲスト人数の差」についてみていきましょう。
結婚式の準備を進める中で、多くの新郎新婦が直面するのが「両家のゲスト数のバランス問題」です。
「お互いのゲストをリストアップしたら新婦側の親族がとても多い…」
「両親から人数は揃えた方が良いと言われてしまった」
など悩んでいる人も多いはず。
そこでこの記事では、両家のゲスト数に差があるのは本当にNGなのか?という疑問にお答えしつつ、ゲスト数に差が出てしまったときに起こる可能性がある問題についてご紹介します。
さらに、人数に偏りがあるときの対処法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
結婚式のゲスト人数の現状と平均
現在の一般的な結婚式のゲスト人数みてみます。

全国平均のゲスト人数
「ゼクシィトレンド調査2024(全国推定値)」によると、披露宴の招待客人数は平均52.0人となっています。人数別の割合を見ると以下のようになっています。
招待客人数別の結婚式割合
- 60~70人未満が14.1%(最多)
- 50~60人未満が11.9%
- 40~50人未満が11.1%
- 30~40人未満が9.7%
- 70~80人未満が9.6%
この結果から、多くのカップルが40~70名程度の中規模な結婚式を選んでいることがわかります。
地域による人数の違い
結婚式のゲスト人数は地域によっても特徴があります。
都市部の傾向
東京や大阪などの都市部では、親族や親しい友人に絞った少人数の結婚式が主流です。
遠方から来るゲストへの配慮や、会場費の高さなども影響しています。
地方の傾向
地方では親族や地域のつながりを重視し、比較的多めのゲスト数になる傾向があります。
特に、三世代が同居する地域では親族の範囲も広く、招待する人数が自然と増える傾向にあります。
文化的背景による違い
家系や地域の慣習によっても招待範囲が変わります。
例えば、親族のつながりを大切にする家系では、従兄弟や叔父叔母まで招待することが一般的な場合もあります。
両家のゲスト数に差があるのはNG?

両家のゲスト数のバランスを考えながら招待するゲストを決めなければならないと思っている新郎新婦も多いですよね。しかし、実際に結婚式を挙げた先輩カップルはあまり人数差を気にしなかったという人がほとんど。
「ゼクシィトレンド調査2024(全国推定値)」によると、結婚式のゲスト数の新郎側・新婦側の比率は「新郎側の方が多い」が29.2%、「新婦側の方が多い」が24.3%、「同程度」が41.3%という結果になっています。無理にゲスト数を調整することなく招待したいと思うゲストに声をかけるというカップルが多くなっており、両家のゲスト数に差があってもOKなのです。
ゲスト数に違いがあるのはよくあること!
新郎新婦が地元から離れて暮らしている場合は親族や友人が遠方にいるため呼びにくいことや、新郎新婦の兄弟姉妹の人数の違い、新郎新婦の職場の規模や職場との関係性など、それぞれの事情によって招待するゲスト数が違うのは自然なことです。
両家のゲスト数に差が出てしまうのはよくあることなので、特に気にする必要がないというのが最近の考え方の主流になっています。
人数差が生まれる理由
- 兄弟姉妹の人数の違い
- 職場の規模や人間関係の差
- 友人の交友範囲の違い
- 地元との距離の違い
- 親族関係の濃淡の差
- 転職や転居による人間関係の変化
時代と共に変わる結婚式の価値観

昔は両家の釣り合いを重視する傾向があり、ゲスト数に偏りがあると片方の家が見劣りするのではないかと考えられることがありました。また、新郎側のゲストより新婦側のゲスト数が多いのは良くないという考えもあり、ゲスト数のバランスを調整する人も多くいました。
しかし、最近では結婚式は「両家の儀式」であるものの「新郎新婦主体のパーティー」という意味合いが強まっています。そのため、ゲスト数を気にすることなく結婚式に来て欲しい人だけを招待するのが主流になっていますよ。ただし、親御さんや親族の中には人数差を気にする人もいるので、ゲスト数に差がある場合は事前に伝えておくといいですね。
現在の結婚式の考え方
- 新郎新婦の意向を最優先
- 形式よりも実質を重視
- ゲストとの関係性を大切にする
- 無理な調整よりも自然体を選ぶ
- 個性やライフスタイルを尊重
招待するゲストをどうやって決めればよいか悩んでいる人は「【結婚式 招待客の決め方】結婚式に誰をどこまで呼ぶのか、人数やバランスを決めるポイント!」で詳しくご紹介しているので、参考にしてみてください!
人数差の実態と許容範囲

一般的な人数差の範囲
実際の結婚式では、どの程度の人数差があるのでしょうか。多くのカップルの事例を見ると、以下のような傾向があります。
軽微な人数差(1~5名程度)
この程度の差は非常に一般的で、ほとんど気にならないレベルです。
席次やレイアウトで簡単に調整できます。
中程度の人数差(6~15名程度)
少し目立つ可能性がありますが、工夫次第で自然に見せることができます。
事前の説明があれば、ゲストも理解してくれるでしょう。
大きな人数差(16名以上)
この場合は何らかの対策を検討した方が良いかもしれません。
ただし、それでも問題ないと考えるカップルも多くいます。
年代別の価値観の違い
人数差に対する考え方は、年代によっても異なります。
20~30代の価値観
- 人数差は気にしない
- 関係性を重視
- 自然体を好む
- 形式にとらわれない
40~50代の価値観
- バランスをある程度重視
- 両家の体面を考慮
- 伝統的な形式を尊重
- 親族の意見を重視
60代以上の価値観
- 両家の釣り合いを重要視
- 格式や体裁を重んじる
- 地域の慣習を大切にする
- 親族の序列を意識する
両家のゲスト数に差があるときに起こるのはこんな問題!
両家のゲスト数に偏りがあるときに起こる可能性があるのは、次のような問題です。
ゲスト数に差があるときは、以下の点に注意してくださいね。
結婚式の費用分担をどのような割合にするのか

まず話し合わなければならないのが、費用分担をどのような割合にするのかということ。
ゲスト数に差があるにも関わらず費用負担は折半するとなると、揉めてしまう原因になってしまいます。ゲストひとりひとりにかかる費用である料理やドリンク、引出物などは人数が増えれば増えるほど費用は高くなりますよね。そのため、折半になってしまうとゲスト数が少ない方は負担に感じてしまうことも。費用負担の割合などどのようにするのか、しっかりと話し合うようにしましょう。
費用分担のパターン
パターン1 完全折半
総費用を新郎新婦で半分ずつ負担する方法です。
シンプルで分かりやすいですが、人数差がある場合は不公平感が生まれる可能性があります。
パターン2 人数比例分担
ゲスト1人当たりの費用を算出し、それぞれの招待人数に応じて負担する方法です。
最も公平性が高い方法といえます。
パターン3 項目別分担
会場費や装花などの共通費用は折半し、料理・引出物などの人数に関わる費用は招待者負担とする方法です。
パターン4 両家の親が負担
両家の親がそれぞれ自分の側の費用を負担する伝統的な方法です。
地域や家庭によってはこのパターンが一般的な場合もあります。
費用分担を決める時のポイント
費用分担を決める際は、以下の点を考慮することが大切です。
話し合いのタイミング
結婚式の準備を始める前に、費用分担について話し合っておくことが重要です。
見積もりが出てから話し合うと、金額の大きさに驚いて冷静な判断ができなくなる可能性があります。
透明性の確保
どの費用をどう分担するのか、明確に決めておきましょう。
曖昧にしておくと後でトラブルの原因になります。
柔軟性の維持
準備を進める中で費用が変動することもあります。
その際の対応方法も事前に決めておくと安心です。
両家の親御さんが両家の人数バランスを気にしてしまう

先ほども触れたように、昔の結婚式のイメージが強い親御さんはゲストに差があることを気にする人もいます。
親族にどう思われるのか、人数が少ないと見劣りするのではないかと親世代ならではの価値観があるようです。また、新郎側のゲスト数を多くするべきと思い込んでしまっている親御さんもいます。
ゲスト数に差がある場合は、まず両家の親御さんに以下のことをしっかりと伝えましょう。
親御さんへの説明ポイント
- 最近では人数差を気にしないカップルが多くなっていること
- ゲスト数を無理に調整するのではなく、本当に来て欲しい人だけを招待したいこと
- 現代の結婚式の価値観について
- お二人の想いや考え方について
それでも親御さんが気にしているようであれば、結婚式・披露宴は親族のみで行い友人のみを招待して1.5次会などを開催する方法もあります。1.5次会については「【結婚式の1.5次会】会費や会場・料理などのスタイルをご紹介!」で詳しくご紹介しているので、参考にしてみてください。
当日の雰囲気への影響
人数差が大きすぎると、当日の雰囲気に影響することもあります。
写真撮影時の問題
集合写真を撮る際に、明らかに人数差が分かってしまう場合があります。
特に、親族集合写真では差が目立ちやすくなります。
歓談時間の違い
ゲスト数が多い方は新郎新婦との会話時間が短くなりがちです。
バランスを取るための工夫が必要になります。
席次表での見た目
席次表を見たときに、明らかに片方の招待者が多いことが分かってしまう場合があります。
人数差が気になるときの対処法
人数差を気にしなくても良いと分かっていても
- 両家のゲスト数の差がかなりある場合
- ゲスト数のバランスがどうしても気になってしまう…
- やはり親御さんが気にしている
など、できるだけ人数差を目立たせたくないと思っている人もいますよね。
ここでは、人数に差があるときの対処法についてご紹介します。
ゲスト数を調整してみる

両家のゲスト数がかなり偏っているときや、どうしても調整したいときはまずゲストの割合を決めて、その後具体的な人数を出しましょう。そして、その人数に合わせて招待するゲストを増やすor減らすようにします。
ゲストを増やす方法
招待するゲストを増やしたいときは、以下の人を検討してみましょう。
追加候補として考えられるゲスト
- グループで交友関係があった友人全員
- 職場関係者(交流のある上司・先輩・同僚・後輩)
- 最近は疎遠になっているが親しかった友人
- 趣味や習い事の仲間
- 近所の方やお世話になった方
- 恩師や先生
ゲストを増やす際の注意点
結婚式の日程が近くなってから声をかけると、人数合わせのために招待されたのかな?と不快な思いをさせてしまう可能性があります。なるべく早めに声をかけるようにしましょう。
また、招待する際は「ぜひ来ていただきたい」という気持ちを込めて、心からお願いすることが大切です。義務的な招待にならないよう注意しましょう。
ゲストを減らす方法
招待するゲストを減らしたいときは、以下のような人がいないか確認してみましょう。
減らす候補として考えられるゲスト
- ゲストの中に知り合いがいない1人で出席する人
- グループでの交流しかなかった人
- 遠方の友人・知人
- 最近連絡を取っていない人
- 職場の義理での招待を考えていた人
ゲストを減らす際の配慮
ゲストを減らすときは、今後の付き合いに影響を与えないように相手への配慮が必要です。
招待できない理由を丁寧に伝えたり、二次会に招待したりと相手に悲しい思いをさせないように心がけましょう。
お詫びの伝え方例
「本当は○○さんにもぜひ来ていただきたいのですが、家族中心の小さな結婚式にすることになりました。改めてお食事でもさせていただければと思います。」
席のレイアウトを工夫する
席のレイアウトを工夫することで、人数差を目立たなくさせることができます。

長テーブルを使用する
円卓の場合、新郎・新婦それぞれのテーブルを作るのが一般的なのでゲスト数に差があると目立ちやすくなってしまいます。長テーブルであれば新郎新婦のゲストが相席で座っても違和感がなく、人数差も分かりにくくなるのでおすすめです。
長テーブルのメリット
- 人数差が分かりにくい
- 会話が生まれやすい
- おしゃれで現代的な印象
- フォトジェニックな仕上がり
長テーブル使用時の注意点
- 端の席の人が疎外感を感じないよう配慮
- 会話しやすい人数での区切り
- テーブル装花の配置調整
円卓の大きさを変える
円卓の大きさを変える方法もあります。人数が多い方を大きな円卓、少ない方を小さめの円卓にしましょう。テーブル数は同じになるので、人数の差が分かりにくくなります。
円卓サイズ調整のポイント
- 大テーブル(10~12名)と小テーブル(6~8名)の組み合わせ
- 会場の広さとのバランス考慮
- ゲスト同士の関係性を重視した配席
新郎新婦友人の混合席を作る
披露宴会場の中心部分に新郎側友人と新婦側友人の混合席を作るのもひとつの方法。席次表の肩書を「新郎新婦友人」にすれば、ゲスト数の差が分かりづらくなります。その場合は、ゲストに混合席になることを事前に伝えておくといいですね。
混合席を成功させるコツ
- 社交的で話しやすい人を中心に配席
- 共通の話題がありそうな人同士を近くに
- 事前にゲストに混合席であることを説明
- 新郎新婦からの簡単な紹介文を用意
席次を工夫する
席次を工夫することで人数差を分かりづらくする方法もあります。

席次表に肩書きを入れない
ゲストに配布する席次表はゲストに席の場所を伝えるためのものですが、肩書きを入れることで新郎新婦との関係性を紹介するという意味合いもあります。
しかし、肩書きが入ることで新郎側なのか新婦側なのかが明白になってしまうため、あえて肩書きを入れない席次表を作る方法も。アットホームな雰囲気の結婚式であればこの方法がおすすめです。肩書きを入れない場合でも、両家両親だけ肩書きを入れるという方法もあります。
肩書きなし席次表のメリット
- 人数差が分からない
- カジュアルで親しみやすい印象
- ゲスト同士の交流促進
- シンプルで見やすいデザイン
席次表を作らずにエスコートカードにする
肩書きが分からないようにする方法として、席次表を作らずにエスコートカードを使う方法もあります。
エスコートカードとは、ゲストの名前とゲストが座るテーブル番号が書かれたカードのことです。受付でゲストにカードを渡してもらい、ゲストはそのカードに書かれた番号のテーブルに着席してもらいます。ゲストに分かりやすいようにテーブルナンバーを用意すると共に、テーブル数が多い場合は披露宴会場入り口にテーブルの配置図を設置しておくと親切。エスコートカードにすれば、席次表がないのでゲスト数が気にならずに済みますね。
エスコートカードの作り方
- カード1枚につき1名の情報を記載
- テーブル番号は分かりやすく大きく表示
- デザインは結婚式のテーマに合わせて
- 受付での配布方法を事前に決定
披露宴を二部制にする
ゲスト数の差が気になるのであれば、思い切って披露宴を二部制にする方法もあります。二部制の結婚式とは、家族・親族のみで「両家の顔合わせ」を目的とした披露宴行い、友人や同僚を招待して「わいわい楽しむ」ことを目的としたカジュアルな披露宴を行う方法です。

二部制のメリット
- ゲストの数が分散される
- 親族が多くて呼べる友人が限られる問題を解決
- 招待したい友人が少なすぎて相手の親族の目が気になる問題を解決
- それぞれのゲストに合わせた演出が可能
- 時間的にゆとりを持てる
また、”本当はカジュアルなパーティーを希望していたけれど親族を招待しないわけにはいかないので諦めていた”などの事情がある人も、このスタイルにすれば悩みが解消されますね。
二部制の一般的なパターン
パターン1 同日開催
【挙式】親族のみ
↓
【披露宴①】親族のみ
↓
【披露宴②】友人・同僚
パターン2 挙式全員参加
【披露宴①】親族のみ
↓
【挙式】親族・友人・同僚
↓
【披露宴②】友人・同僚
この場合は、挙式前に披露宴を行うことを両家の親御さんや親族に了承を得ておくようにしてくださいね。
パターン3 別日開催
挙式+披露宴を親族のみで行い、後日友人や同僚などを招待して披露宴を行う方法もあります。
準備期間中の注意点

早めのコミュニケーション
人数差がある場合は、準備の早い段階で関係者とのコミュニケーションを取ることが重要です。
両家の親との話し合い
- 人数差について早めに報告
- 現代の結婚式事情を説明
- お互いの価値観を尊重
会場との相談
- 席次レイアウトの可能性確認
- 追加オプションの検討
- 当日の配慮事項の相談
ゲストへの配慮
人数差があることを事前にゲストに伝える必要はありませんが、当日困らないような配慮は必要です。
分かりやすい案内
- 受付での丁寧な案内
- 席次図の見やすい配置
- スタッフへの事前説明
交流促進の工夫
- 歓談時間の確保
- 自己紹介タイムの設定
- 新郎新婦からのゲスト紹介
まとめ
今回は両家のゲスト数に差がある場合の問題や対処法についてご紹介しました。
ご紹介したように両家のゲスト数に差があるのはよくあることで、決してNGではありません。最近では人数差を気にしないという人が多くなっています。
現代の結婚式では、形式的なバランスよりも、新郎新婦の想いや価値観を重視する傾向が強まっています。大切なのは、招待したいと思う人を心を込めて招待し、来てくれるゲスト一人ひとりに感謝の気持ちを伝えることです。
しかし、どうしても気になる場合はご紹介したような対処法を取り入れることで、人数差を感じることなく結婚式を進められるでしょう。席次の工夫や会場レイアウトの調整、場合によっては二部制の検討など、様々な解決策があります。
また、人数差を問題として捉えるのではなく、それぞれの特徴を活かしたポジティブな発想も大切です。人数が少ない方はより親密で質の高いおもてなしを、人数が多い方は賑やかで華やかな演出を心がけることで、どちらも素晴らしい結婚式になります。
準備を進めていると人数差が気になってしまうこともあるかと思いますが、大切なことは来てくれるゲストひとりひとりにどのように感謝の気持ちを伝えられるか考えることです。
両家の親御さんとも十分にコミュニケーションを取り、お互いの価値観を尊重しながら、全員が納得できる結婚式を目指しましょう。
この記事を参考に、ゲストの人数差があったとしてもゲストにおもてなしの気持ちを伝えて、楽しんでもらえる結婚式を作ってくださいね!きっと、参列した全ての方の心に残る、愛に満ちた特別な一日となることでしょう。